【大学受験の教訓】文系・理系は得意科目から選ぶべき!私の失敗談とアドバイス
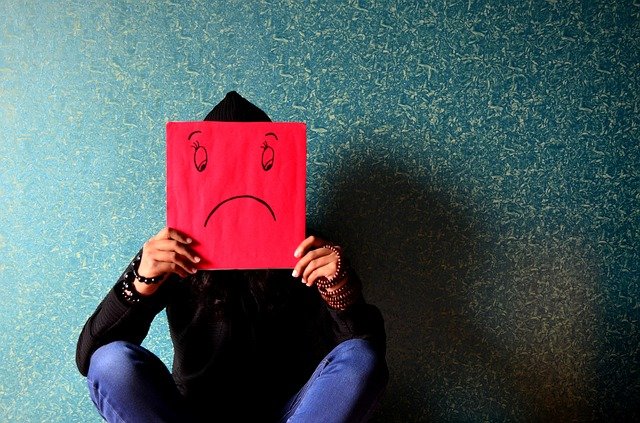
文系と理系のどちらにしようかな?
高校生にとって、 「文系・理系の選択」 は大きな分岐点ですよね。学校によりますが、高校2年生には選択を迫られるのが一般的です。
私も高校時代、文系か理系か悩む間もなく、深く考えずに「理系」を選びました。しかし、 この短絡的な決断が後に大きな苦しみをもたらすことになりました。
高校2年生から現役受験までは理系として(数Ⅲあり)勉強しましたが、結果は散々。浪人するタイミングで 文転(文系に変更) を決断し、ようやく「自分に合った場所」を見つけることができました。
この記事では、理系として無理に2年間過ごし、浪人時に文転した経験から得た教訓をお伝えします。文系・理系の選択に悩んでいる方に向けて、 「得意科目から選ぶべき理由」 を具体的に解説します!
※本コンテンツはプロモーション(PR)を含みます。
Contents
文系・理系の選択は得意科目を基準にするべき
私が理系を選んだ理由
高校1年生の終わり、私は深く考えずに理系を選択しました。当時、「医者になりたい」という漠然とした夢があり、また理系の兄への憧れもありました。「理系科目もできる」と自分に言い聞かせていたのです。
理系で直面した苦難
高校2年生になると、数学(数Ⅲ)や物理・化学など理系特有の難解な内容に苦しむようになりました。赤点を取ることもあり、頑張っても成績は伸びません。一方で、国語や地理といった文系科目ではクラストップの成績を収め、友人からも「どう見ても文系向き」と言われるほどでした。
それでも、社会科目が2科目必要な文系への転向(文転)は負担が増えると思い、理系で突き進むことを選びました。
浪人時に文転を選んだ理由
現役時代の受験ではセンター試験で7割未満の成績しか取れず、京都大学を含む志望校は全て不合格。浪人を決意した際、ようやく 「文転」 を選択しました。その理由はシンプルに「文系科目が得意だったから」です。
文転後は、理系特有の科目から解放され、得意な国語や社会科目に集中できたため、勉強が楽しく感じられるようになりました。
なりたい職業を考えることも重要
文系・理系選択が職業に与える影響
文系・理系の選択は、将来の職業にも直結します。たとえば、現役時代の私は医者という目標があったため理系を選びましたが、高校3年生になる頃にはその志望が薄れ、文系学部への興味が湧いていました。
「もっと早く志望学部や将来の職業をしっかり考えていれば、文系へ切り替える判断ができたのに…」と今でも後悔しています。
逆パターンも存在する
一方で、文系を選んだ友人の中には、後に農学部を目指したいと思い立ったものの、理転(文系から理系への変更)はハードルが高く断念した例もありました。
このように、文系・理系の選択は一見小さな決断に思えても、将来の進路や職業に大きな影響を及ぼします。
得意科目を武器にする重要性
得意科目がもたらすメリット
浪人時に文転を決断したことで、得意科目を最大限に活かせるようになりました。京都大学の二次試験(社会科目の記述・論述問題)では、得意だった地理で7割以上の得点を達成。社会科目だけで見ると合格圏内の成績を取ることができました。
一方、現役時代に苦手な理系科目を克服しようとした努力は、時間も労力もかかり、結果的には非効率でした。 得意科目を武器にすることで、短期間で効率よく結果を出せる と実感しています。
まとめ:進路選択で得意を活かそう!
文系・理系の選択は、その後の受験生活や将来のキャリアに大きな影響を与える重要な決断です。私の経験から、以下の教訓をお伝えします:
- 得意科目を基準に選ぶ
- なりたい職業を考慮する
- 苦手を克服するより、得意を伸ばすほうが効率的
自分に合った進路を選び、後悔のない受験生活を送ってください!


